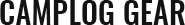生活感バリバリの消耗品をキャンプサイトに置いておくと日常感が出てしまうため、「ちょっと…」と感じる方も多いのではないでしょうか?
そういった方は、詰め替えをしたり、ケースに入れて商品ラベルが見えないようにしたりと、いろいろと工夫されているかと思います。
筆者もその一人。
ペーパータオルケースを探していたところ、オレゴニアンキャンパーのティッシュケースが気になりポチリ。
使い勝手などレビューしていきたいと思います。
Oregonian Camper BOX TISSUE CASE
今まで感じていた不便

撮影:筆者

撮影:筆者

撮影:筆者
今まではロールタイプのキッチンペーパーと、それに対応したケースを使用していました。
キッチンペーパーそのままだと、朝露やにわか雨でペーパーがだめになってしまったことがあり、ケースを使い始めたのですが…。
これがめちゃくちゃ使い勝手が悪い。
中の芯を抜いて、中心部分からキッチンペーパーを引っ張るように出すのですが、途中で切れたり出てこなかったりと不満たらたら。
そんな不満が積もり積もって、ロールタイプからペーパータオルへ使用をシフト。
これが楽ちん!そして便利!
ですが、テーブルに置いておくのは邪魔になるため、ポールなどにぶら下げて使えるようにケースを使うことにしました。
そんな時に見つけたのが、この商品です。
編み込みパラコードのハンドルがいい感じ

撮影:筆者
使いたい場所に吊り下げておけるので、テーブルがごちゃごちゃにならず、サイトがすっきりします。

撮影:筆者

撮影:筆者
バックル付きです。
セットの仕方
1.開く

撮影:筆者

撮影:筆者
2.ティッシュをセットする

撮影:筆者
多い場合は、中身を抜いて必要分を入れます。
3.ふたを閉じる

撮影:筆者
セット可能なティッシュについて

撮影:筆者
家にあった4種類のティッシュ・ペーパータオルで試してみました。
ペーパータオル

撮影:筆者
200枚入りのペーパータオルです。
すべては入らなかったため、中身を取り出して入る分だけ入れました。
箱ティッシュ(大きめ)

撮影:筆者
箱自体は要りません。
ペーパータオルと同じように中身を取り出せば入れることができます。
箱ティッシュ(通常サイズ)

撮影:筆者
箱ごと入りました。
パックティッシュ

撮影:筆者
袋ごと入ります。
後ろのベルトは車のヘッドレスト用

撮影:筆者

撮影:筆者
背面には2本のベルトがあります。
ボタン止めになっており、一応外せますが…
めちゃくちゃかたいので、ボタンを外すのは大変です。

撮影:筆者

撮影:筆者
車のヘッドレストにぴったりということでしたので、実際に装着してみました。
なかなかいい感じです。
AIからのおすすめ
以下は、Oregonian Camper BOX TISSUE CASE (BLACK CAMO)と組み合わせてアウトドア活動をより楽しむためのアイテムの具体例です。
1. **ポータブル折り畳み椅子**
– アウトドアでの休憩やピクニックに便利なポータブル椅子は、快適な座り心地を提供します。
BOX TISSUE CASEと組み合わせることで、快適な休憩スペースを確保できます。
– アウトドアで飲み物や食品を保冷するのに便利なクーラーバッグは、ピクニックやキャンプなどで重宝します。
Oregonian Camper BOX TISSUE CASEと組み合わせることで、食品や飲み物を保管する際に便利です。
– 暑い日や湿度の高い日にアウトドアで快適さを保つためのハンドヘルドファンは、必需品です。
BOX TISSUE CASEと組み合わせることで、暑さ対策をしながら快適にアウトドア活動を楽しめます。
– アウトドアで座る場所を確保するための折りたたみ式ピクニックブランケットは、草地や砂浜などで快適な座り心地を提供します。
Oregonian Camper BOX TISSUE CASEと組み合わせることで、アウトドアでのくつろぎスペースを確保できます。
– アウトドアでの夜間の活動やキャンプ場での照明として便利なハンディLEDライトは、安全性や便利さを提供します。
BOX TISSUE CASEと組み合わせることで、夜間のアウトドア活動をサポートします。
※当コンテンツはAIによる自動生成のため、正確性に欠ける場合がございます。
まとめ
Oregonian Camperのボックスティッシュケースは、生活感を隠してサイトをすっきりさせるにはぴったりのアイテムです。
また、日常にアウトドアの要素を入れたい人にもおすすめです!
ティッシュケースとしては高めの商品ではありますが、型崩れもしづらく、吊り下げて使うためのハンドルもあるので、個人的には買ってよかったと感じています。
ティッシュケースの購入を検討している方は、参考にしていただけると嬉しいです。
written by 水木 幸